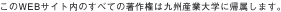科目名: 耐震工学特論
担当者: 楢橋 秀衞
| 対象学年 | クラス | [001] | |
| 講義室 | 開講学期 | 前期 | |
| 曜日・時限 | 単位区分 | ||
| 授業形態 | 一般講義 | 単位数 |
| 準備事項 | |
| 備考 |
| 講義の目的・ねらい(講義概要) | 学部では土木・建築構造物の設計用地震荷重について学んだことだろう。本科目では、近年の地震動研究の成果を踏まえた耐震設計用入力地震動の考え方、既存不適格構造物の耐震補強問題と補強技術、巨大地震に伴う長周期地震動がもたらす影響と対策、地震リスクマネジメントの概念などについて、最新の知識を学ぶ。 |
| 講義内容・演習方法(講義企画) | ①地震被害の種類 震動、地変、火災、津波による被害 ②阪神大震災の教訓 兵庫県南部地震の被害記録の再確認 ③活断層と地震活動(1) 活動度、地震規模、トレンチ ④活断層と地震活動(2) 長期発生確率の推定 ⑤荷重のバラツキ 設計用荷重のバラツキと確率処理 ⑥地震荷重と再現間隔 地震荷重の再現間隔、極値、限界状態設計法と設計規準 ⑦演習課題(1回目) 講義第1回~6回の範囲 ⑧地震動予測(1) 震源過程、経路、S波速度、工学基盤 ⑨地震動予測(2) 地盤、増幅、設計用地震動 ⑩地震災害と対策 被災構造物の応急危険度判定、耐震診断と補強 ⑪免震、制震 地震安全確保の新しい技術 ⑫巨大地震と長周期地震動 大規模構造物と長周期地震動の影響 ⑬地震リスク解析 地震災害の社会に対する影響 ⑭演習課題(2回目) 講義第8回~13回の範囲 |
| 評価方法・評価基準 | 演習課題(2回、各50%)により評価する。60点以上を合格とする。 |
| 履修の条件(受講上の注意) | 受講手続きの前に、担当者に講義の内容を問い合わせること。 |
| 教科書 | なし (資料を配付する) |
| 参考文献 | 1)池田俊雄監修「活断層調査から耐震設計まで」鹿島出版会 2)日本道路協会「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編」丸善 3)太田外気晴ほか「巨大地震と大規模構造物」共立出版 4)中村孝明ほか「地震リスクマネジメント」技報堂出版 |
| 特記事項(その他) |